経営改善
2020/06/22
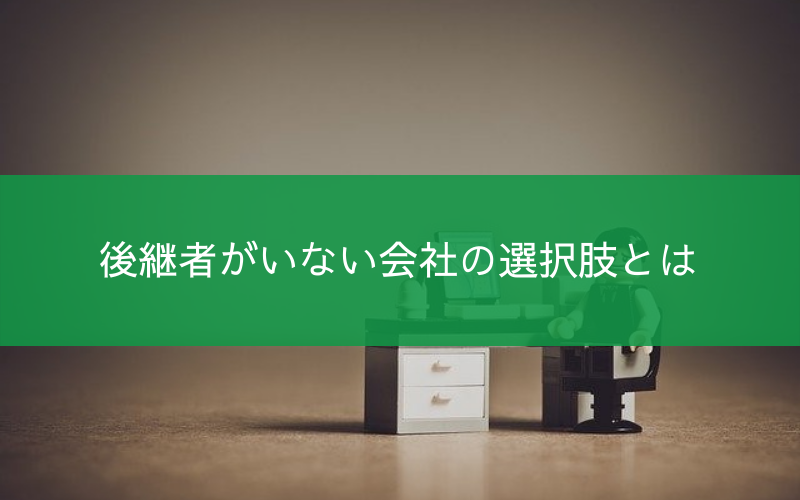
中小企業における後継者問題は年々深刻化の一途を辿っています。
後継者を誰にすべきか、そもそも後継者がいない場合はどうするべきかなど、事業継承についての経営判断に悩んでいる経営者は少なくありません。
今回は、後継者問題の実態を踏まえながら、第三者への継承や、M&A、事業継承ファンドの活用など、経営者として知っておくべき解決策をご紹介します。
目次

企業経営者にとって会社の後継者問題は避けて通れない問題です。後継者がいないことで廃業を余儀なくされる中小企業も増えています。
中小企業庁のデータによると、中小企業の多くの社長が高齢化を迎える2025年には、127万社が後継者不在となって650万人の雇用が失われるというデータが示され大きな注目を集めました。
自社事業を安定して継続させるためには、経営者が退く年齢までの猶予を考えながら後継者を選んでおかなければなりません。
しかし、実際には少子高齢化による後継者不在、子どもが事業に興味を持っていない、親族間のトラブル回避などの理由で、後継者として適した人材に恵まれない、後継者を選べないケースは多いです。
後継者は早めに選定し、優れた経営者として育成する必要があるのに、そもそも適任者がいないまま対策をしていないという経営者も少なくありません。
もし、後継者がいるなら選択肢は2つあります。
日本の中小企業では親族間で跡継ぎを選んで事業継承する方法が伝統的に行われてきました。
親族内で継承することには多くのメリットがあります。まずは、後継者が若い頃から事業継承の覚悟を持って、長期的な教育が可能となる点です。
経営者としての考え方を学び、現場を知ってより良い後継者としての成長が期待できます。また、従業員や取引先にとっても受け入れやすく、実現しやすい点がメリットと言えるでしょう。
ただし、親族内での事業継承にはデメリットもあります。会社事業を先代から受け継ぐ場合には、同時に相続問題も発生するので、兄弟関係や親子関係、配偶者を巻き込んで親族トラブルになるケースが少なくありません。
さらに、跡継ぎの経営者としての能力不足や、リーダーシップ不足などが不安材料となる場合もあるでしょう。また、人間関係の問題、資金繰りの悩み、借入の連帯保証債務の問題など、経営者となると多くの責任やストレスを抱えます。経営者としては、そういった苦労を親族にはさせたくないと考え、承継をさせないと判断することもあります。
そのため、あえて親族外の従業員などに事業継承をするという選択肢もあります。そうすると親族外から広い視点で後継者を選べる上、現場を知り、会社や業界の状況を知っている人材で、新しい経営者にふさわしい人に会社の未来を任せられる点がメリットとなるでしょう。
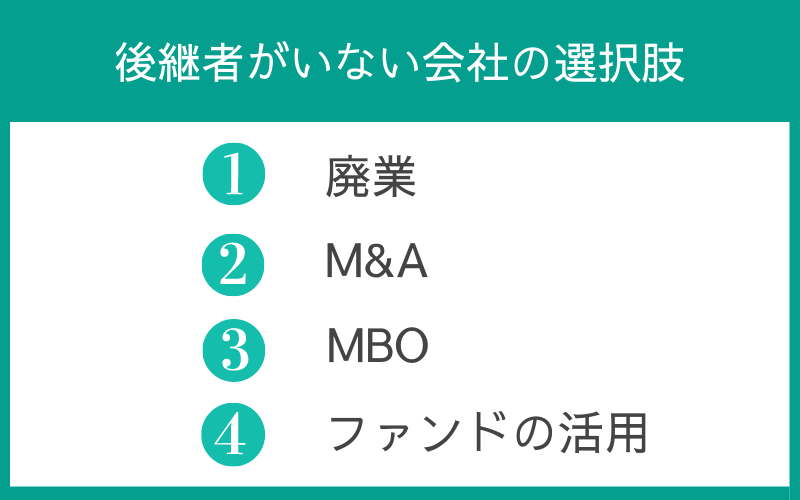
親族内にも親族外にも後継者として適任の人材がいない場合、選択肢は4つ
です。
後継者がいない中小企業の多くが廃業に追い込まれています。会社を設立した際に、自分の代で廃業することを決めていた社長もいるでしょう。
しかし、廃業にはデメリットが多く、最も避けたい選択肢と言っても過言ではありません。
まず、会社を廃業すれば既存の従業員が職を失うことになります。今まで働いてくれた従業員を全員解雇するということは、経営者として非常に辛い選択肢なのではないでしょうか。
また、会社を廃業すれば既存の取引先にも影響を与えることになります。取引先が少ない中小企業にとっては、廃業の影響で経営が傾くことも珍しくなく、連鎖的に廃業という可能性も否定できません。
さらに、会社を廃業するためにもお金や時間が必要な点を知っておきましょう。廃業には約1年半程度の時間が必要で、その期間は通常業務を行いながら廃業の準備をすることになります。
後継者不足だから、自分が興した会社だからといって、安易に廃業を選択することは避けましょう。
後継者がいない場合の選択肢の一つとしてM&Aは有効です。M&Aとは会社の経営権を売買することを指します。
会社の事業を他の会社に売却して対価を受け取れるので、法人税と比較して低い税率でキャッシュが手に入ります。買手企業の下で会社の事業を存続できる手法です。
会社ごと第三者へ引継ぎますので、取引先、従業員にも迷惑をかけずに、経営から退くことができます。これは経営者にとってのメリットも大きい選択肢と言えます。
買い手が別会社となるM&Aに対して、MBOの買い手は会社の経営陣となります。つまり、外部の人間ではなく部内者に会社の経営権を売却するのがMBOです。
部内での事業継承となるため、企業文化やブランドの維持、事業の理解度の高さなどがメリットとなります。
事業継承でM&Aを選択した場合、買手企業の目的によっては買収後に相手企業に取り込まれるケースも多いです。その場合、大切な従業員や愛着のあるブランドなどがないがしろにされることもあるでしょう。
もし、自分の会社の理念や社風を大切にしながら事業継承を行いたい場合は、ファンドの活用をおすすめします。事業継承ファンドを活用すると、企業価値を高めながら事業拡大へ向かって舵を切っていけると考えて良いでしょう。
もちろん、ファンドの手法が企業理念や社風、企業文化を尊重しながら利益追求するという方針かどうかの見極めは大切となります。
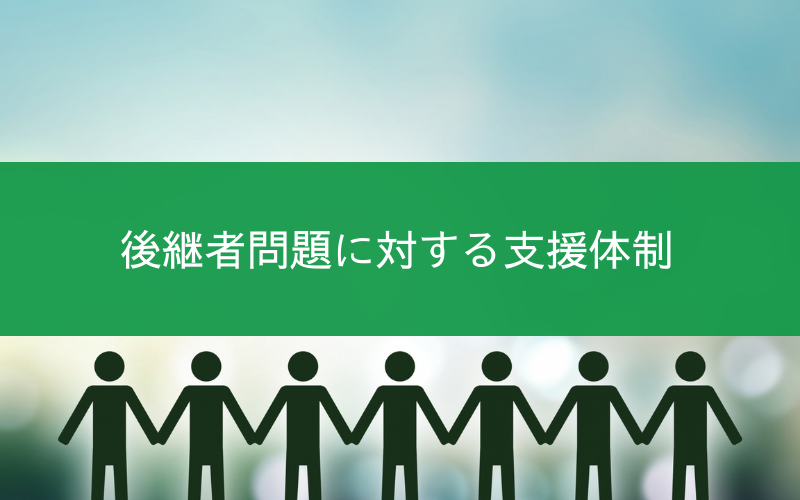
後継者がいない会社経営者の悩みを解決するために、国や自治体などでは支援体制を構築しています。東京都を例に挙げ、具体的にどのようなサポートが受けられるのか、どういった活用ができるのかをご紹介します。
東京都事業承継・引き継ぎ支援センターは、国の事業で設置されており、東京商工会議所が経済産業省関東経済産業局から委託を受けて実施しています。
後継者が不在で困っている中小企業に対し、情報提供や専門の支援機関をつないで支援を行っています。M&Aに関する相談が無料でできます。
また、後継者人材バンクも事業の一つです。後継者がいなくて悩んでいる企業経営者に対して、起業を目指す人材をマッチングさせて後継者不足の解決を目指しています。
事業承継補助金とは、事業承継をきっかけに新しい取り組みを行おうとしている承継者に向けて行われる補助金制度です。
事業承継補助金にはⅠ型(後継者承継支援型)とⅡ型(事業再編・事業統合支援型)があり、それぞれ目的と補助金額が異なります。
Ⅰ型は後継者承継支援型で、経営者が交代するにあたり、新しい取り組みを実施する際に使われる経費の一部を補助するための支援です。補助金は小規模事業者の場合、上限額が200万円で補助率は2/3、それ以外の事業者の場合、上限額が150万円で補助率は1/2です。
さらに、事業所を廃止したり事業自体を集約・廃止したりする場合は、最大300万円を上乗せさせることもできます。
Ⅱ型は事業再編・事業統合支援型で、M&Aを実施し、新しい取り組みを行おうとしている承継者に向けて行われます。Ⅰ型と違う点は、上限額が審査結果に応じて異なるという点です。
審査結果が上位であれば上限額は600万円で補助率は2/3、上乗せは最大600万円となります。一方、上位に入れなかった場合は上限額450万円で補助率は1/2、上乗せは最大450万円です。
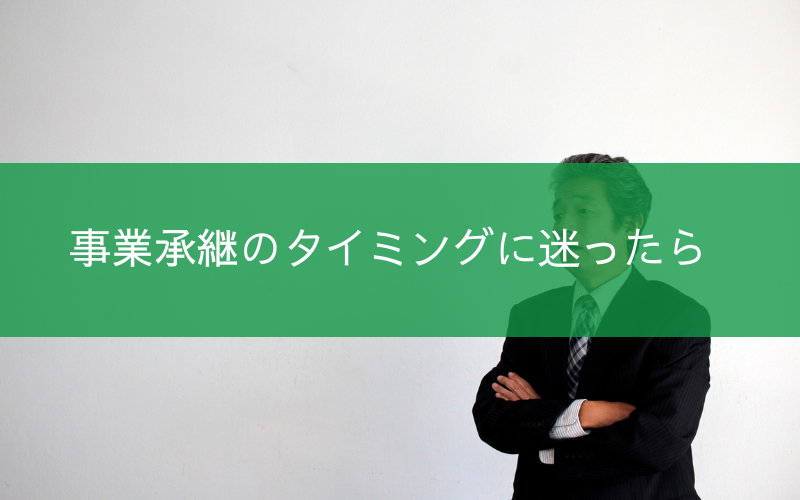
そもそも事業承継をするかどうかで迷ったとき、企業価値を見て事業承継をするかどうか判断するとよいでしょう。
自社の企業価値はM&Aで価格を交渉する際に判断基準として設けられる重要な項目で、なおかつ相続税の評価や経営戦略の策定などに活用できます。
企業価値を算出する手段にはさまざまなものがありますが、将来予想される収益まで考慮し、現在の企業価値として算出する「インカム・アプローチ」が定番の方法です。
なかでもDCF法はインカム・アプローチの中でも代表的な算出方法として知られています。DCF法は企業の将来性を分析できるため、事業承継の判断にも利用しやすいでしょう。
ただし、算出するまでに手間がかかる点はデメリットの一つと言えます。
企業価値を算出したところでどのように評価すればいいのか分からない場合は、最初からM&Aの専門家に相談してみるのもおすすめです。
M&Aの専門家なら、いつ事業承継をするべきか正しく判断してくれますし、企業価値の評価をしてくれます。無料で行っているところも多いので積極的に利用するとよいでしょう。
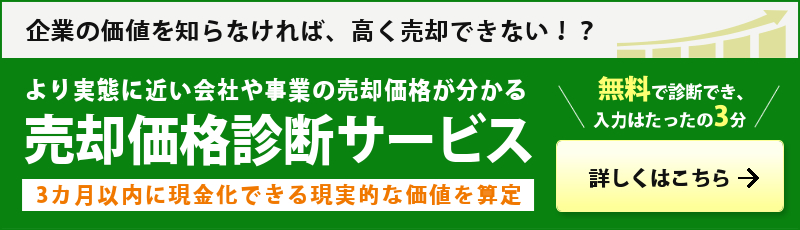

後継者候補はいるものの、本当にこの人でよいのか迷うことがあるかもしれません。そんなときは、後継者が今後自社を成長させていく経営者になれるかどうか、判断基準を設けて適うか見ていきましょう。
判断基準として以下の4つは必ず見ておきたいポイントと言えます。
・経営する意欲があるか、経営者としての意識を持っているか
・経営理念を共有できるか
・社員から信頼を得られるような人物か
・取引先などと信頼関係を築けるか
親族や社内にこれらの適正に適う人物がいれば良いのですが、もし見当たらないようなら勇気を持って「引き継がせない」という決断をすることも大切です。
そうした場合は、第三者への事業承継を検討や、それでも難しければ他社への承継を検討してみましょう。

現在の経営状況が芳しくなく、債務超過に陥っている場合も選択肢は存在します。債務超過がある企業にはどのような選択肢があるのか、ご紹介します。
後継者が不在、なおかつ債務超過にも陥っているというのであれば、廃業もしくは倒産も選択肢の一つに入ります。
多くの方は廃業や倒産のこちらの選択肢ばかりに目を向けてしまいがちですが、廃業もしくは倒産によるデメリットは多くあります。
例えば従業員を全員解雇しなくてはならなかったり、取引先との関係性が全てなくなったりする点が挙げられます。
また、廃業・倒産に基づき資産を売却しようとした際に、低い見積もりで清算しなくてはいけない場合もあります。これは、資産というものは事業を継続しているからこそ価値のあるもので、廃業・倒産が決まっている状態で売却しても高値が付きにくいためです。
場合によっては設備の解体・処分にコストが発生する可能性もゼロではありません。第三者への譲渡が検討できる財務状況であるならば、第三者への譲渡を検討するべきです。
同じ倒産であっても、よりダメージの少ない(迷惑を最小限に抑えた)かたちで、会社の清算ができる可能性があります。
親族や従業員へ事業譲渡をしたいとなっても、債務超過がある企業を経営したいと思う人は少ないでしょう。しかし、第三者への譲渡による承継なら債務超過があったとしても事業承継が行える可能性があります。
なぜ債務超過があっても事業承継が可能なのでしょうか?
その理由は、買手側にとって事業のシナジー効果を得られること、現在は赤字でも将来的に成長が見込めること、他社に負けない独自の無形資産(技術やブランドなど)を保有していることなどが挙げられます。
また、買手側にとって債務超過がある会社を買収しようとした場合、一般的な企業よりも安価で手に入れられる可能性が高いです。このような理由から、債務超過がある会社でも第三者へ譲渡することはできます。
中小企業における後継者不足の問題は年々深刻化していますが、現在の状況によってさまざまな選択肢があります。
後継者がいない場合の選択肢
・廃業
・M&A
・MBO
・ファンドの活用
上記の選択肢から自社にとって最適な方法を見極め、選ぶことが大切です。
後継者がいなくて悩んでいる経営者は、M&Aを選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか?
まずは専門家に相談し、事業を継続するための方法を探っていきましょう。
2019/09/25
2019/10/17
2018/08/19
2019/08/09
ご相談は無料です。お気軽にお声かけください。
Copyright© 2021 MAIN.co.ltd. All Rights Reserved.