M&A
2019/12/24

事業譲渡において、最も重視しなくてはいけないポイントは「各種契約・許認可の名義変更」です。
もしも契約や許認可の変更が行えていなかった場合、そもそも事業譲渡が成り立っていないことになります。
このようなリスクを回避するためにも、あらかじめ事業譲渡における注意点について理解しておく必要があるでしょう。
今回は事業譲渡の注意点について、具体例を挙げながら解説していきます。
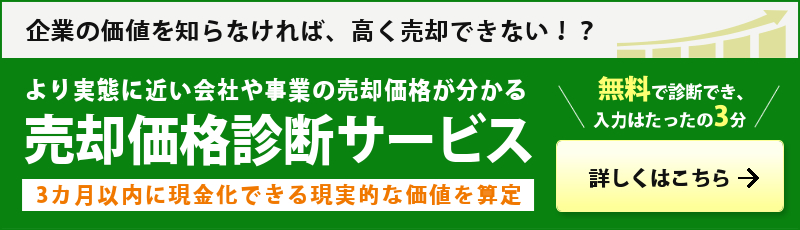
目次
まずは事業譲渡の基礎知識を改めて理解していきましょう。
事業譲渡とは、事業の一部もしくは1つの事業すべてを別の会社へ売却することを指します。
売り手側は会社経営を続けながら再建に向けて取り組めますし、買い手側にとっても事業規模を拡大させたり、新たな顧客・取引先の獲得、人材や技術・ノウハウの取得が行えたりします。
事業譲渡を行うメリットは、会社を継続できるという点です。
M&Aスキームの一つである「株式譲渡」を行った場合、会社をそのまま売却することになるため、会社自体は残っても実質的な経営は譲受会社側に移ってしまいます。
しかし、事業譲渡なら事業だけを切り離すことになるため、会社の経営はそのまま継続して行うことができます。
また、不採算事業を売り渡し、その譲渡益を成長事業に追加投資することもできます。
事業譲渡を行えば、法人格を残しながら不採算事業を切り、成長事業に投資して新たな一歩を踏み出すことも可能です。
さまざまなメリットが得られる事業譲渡ですが、デメリットも存在します。
例えば株式譲渡に比べて手続きも煩雑になり、手間がかかりやすい点が挙げられます。
特に企業規模が大きければ大きいほど、会社の負担は大きくなっていくでしょう。
また、事業譲渡では売り手側に譲渡益(利益)が計上されますが、この譲渡益をそのまま利益として計上すれば3割もの法人税が課せられてしまいます。
株式譲渡では法人税がかからないため、より多くの譲渡益が手元に残りやすいです。
事業譲渡の場合、合併や会社分割のようなすべての権利・債務が移転されるわけではなく、あくまでも一事業のすべてもしくは一部を譲渡する契約になります。
会社のすべてが承継されないため、当たり前のように権利や財産が譲渡されるわけではありません。
もし、不採算だった健康食品事業を譲渡したいと考えた場合、健康食品を製造するための工場や設備などの資産は、勝手に譲受会社へ渡るわけではないのです。
後ほど詳しくご紹介しますが、権利・財産を譲受会社へ移転させるには、個別に移転する必要があります。
また、健康食品事業で赤字が出ていたとしても、譲受会社は債務(負債や借金)まで引き継ぐこともありません。
事業の個別財産の所有権や契約上の地位を移転するためには、手続きが必要となってきます。
特に、事業譲渡に伴い譲受会社へ移転させたいものが多くなると、その分手続きも煩雑になり、名義移転を行う際には費用までかかってしまいます。
譲受会社との間で移転の合意を取っただけで移転することはできず、きちんと「移転した」という事実が明確になるよう、財産ごとに第三者への対抗要件も備えておく必要があります。
具体的に、どのような移転手続きや対抗要件が財産・権利ごとに必要となってくるのか、健康食品の工場を例にとって解説していきましょう。
事業譲渡を行う上で、工場などの不動産の所有権も譲渡しなくてはならない場合、第三者への対抗要件として「所有権移転登記」を準備する必要があります。
また、不動産の抵当権・地上権などがある場合も、移転登記を用意しなくてはなりません。
根抵当権の場合は、元本が確定する前に債務引き受けが実施された場合に、根抵当権者が引受人の債務につくため権利を行使できなくなってしまいます。
権利をきちんと行使できるようにするためにも、あらかじめ債務者の変更登記を行っておく必要があります。
さらに、不動産の名義変更を行う場合には、不動産取得税や登録免許税などのコストが発生するので注意してください。
健康食品を製造する工場にはたくさんの設備が配置されています。
製造に使われるような機械設備や製品そのもの、貯蔵品に加え、対象事業に関わる様々な備品などもすべて「動産」に分類されます。
動産は、譲渡契約を結ぶと当事者間で所有権が移転されますが、第三者へ対抗するためには譲渡日に引渡しを実施しなければなりません。
また、事業の中で取引先やサービス事業者とのさまざまな契約が結ばれているかと思いますが、この契約も一つずつ個別に対応し、更改する必要があります。
契約しているものはすべて再締結しなくてはなりませんが、例えば賃貸契約や電気・ガス・水道・インターネット契約なども、名義変更が必要となります。
特に注意しておきたいのは、知的財産権です。
創作物や工業所有権などに対して、有体物と同様の財産権利を持てる知的財産権は、特許権のように登録すると移転による効力が生じるため、継続的に活用する場合は移転手続きが必須となります。
事業に関連する財産や権利以外に、従業員も全員がそのまま譲受会社へ移転されるわけではありません。
譲受会社への移転には、従業員一人ひとりから個別に同意を得る必要があります。
個別に同意を得なくてはいけないということは、事業譲渡に賛同できない従業員は退職してしまう可能性もあるのです。
技術やノウハウを持った従業員は非常に貴重な存在であるため、なるべく退職者を出さないようにすることが事業譲渡を成功させるための、1つのポイントとなってくるでしょう。
従業員を退職させないためには、事業譲渡を行うことを伝えるタイミングと丁寧な説明は必須となります。
誤ったタイミングで伝えてしまったり、説明の仕方を間違えたりすると、たくさんの退職者が出てしまうかもしれないので注意しましょう。
経験豊富なアドバイザーからの意見を聞きながら、丁寧に対応していくと退職者を減らすこともできます。
競業避止義務は、会社法21条で譲渡会社に対し定められているもので、譲受会社が不利益を被るような競業行為を禁じています。
具体的には、譲渡会社が不採算事業を切り離し、譲受会社へ売却したとします。
しかし、その後譲渡会社はこれまで行ってきた事業のノウハウや経験が残っており、再び同じ事業をスタートさせました。
こうなってしまうと譲受会社と譲渡会社は同市場の競合関係にあたってしまい、シェア争いへと発展してしまうでしょう。
譲受会社はせっかく事業を買収したのに目的が達成できなくなってしまい、信義則にも反してしまいます。
こうした事例が発生しないよう、会社法21条では「同一の市町村及び隣接市町村も含め、その区域内で譲渡日から20年間は同じ事業を行ってはいけない」と定めているのです。
ちなみに会社法では20年間となっていますが、双方同意の上契約を結べば最大30年まで延長させることもできます。
譲渡損益は、譲渡対価と譲渡対象になる簿価純資産の差額から計上されます。
もしも譲渡益を得た場合、その他の所得と合わさって法人税の対象となるので注意してください。
譲受会社では譲渡された事業に関連する資産・負債は、それぞれ時価で引き継ぐ必要があります。
従業員の退職給付債務などの負債も認識し、譲渡対価と事業に関連する時価純資産の差額がのれん代となり、資産調整勘定や差額負債調整勘定として計上します。
ここで出た金額を5年で均等償却していかなくてはなりません。
ただし、土地や有価証券、事業の売掛金については非課税対象となります。
また、資産の中には消費税の課税対象となる資産もあるので、間違えないように注意しましょう。
事業譲渡の契約書には収入印紙を貼り付ける必要があります。
もしも印紙税を納めなかった場合、追徴課税として元の額の3倍を支払わなくてはならないので気を付けてください。
事業譲渡の契約書が分類される「1号文書」で納める印紙税額は以下の通りです。
1万円未満…非課税
1万円以上10万円以下…200円
10万円超え~50万円以下…400円
50万円超え~100万円以下…1,000円
100万円超え~500万円以下…2,000円
500万円超え~1,000万円以下…1万円
1,000万円超え~5,000万円以下…2万円
5,000万円超え~1億円以下…6万円
1億円超え~5億円以下…10万円
5億円超え~10億円以下…20万円
10億円超え~50億円以下…40万円
50億円超え~…60万円
ちなみに、契約金額の記載がない場合、印紙税額は200円となります。

ここまで事業譲渡における注意点をいくつかご紹介してきましたが、具体的な事業譲渡の流れの中でどんな点に注意していけば良いのか分からない方もいらっしゃるかと思います。
そこで、事業譲渡の契約から決済完了まで、それぞれの行程で注意すべきポイントをご紹介していきます。
事業譲渡を行う前に、そもそも事業を売却できるのか、事業譲渡によって自社が大きなメリットを得られるのか調査することが大切です。
例えば、自社の現状を把握し、強みや市場価値を細かく分析していきます。
分析結果から事業すべてを売却するのか、それとも一部を売却するのかを決め、どれくらいで売るべきなのかを考えてみましょう。
また、事業譲渡におけるプランニングも大まかなものより、詳細に構築することで次の取締役会での承認も得られやすくなります。
自社分析やプランニングが不十分だと、事業譲渡自体が失敗してしまう可能性もあるので注意が必要です。
売り手企業は事業譲渡に入る前に、取締役会で承認を得なくてはなりません。
事業譲渡をなぜ行うのか、目的や理由をしっかりと説明しておきましょう。
取締役員から過半数以上承認を得れば、本格的なスタートとなります。
事業譲渡を成功させるためには、アドバイザーへ依頼した方が良いでしょう。
アドバイザーは適切なアドバイスを送ってくれるだけでなく、条件に合う買い手企業を見つけてくれたり、交渉を有利にさせてくれたりと、様々な恩恵が受けられます。
アドバイザーを依頼する際には、事業譲渡の経験・実績が豊富で、信頼できる専門家を選ぶと安心です。
買い手企業を探す前に、条件面を設定しておきます。
あまりにも売り手企業だけに有益な条件を設定してしまうと、買い手企業は見つかりません。
アドバイザーと相談しながら適切な条件を決めていきましょう。
アドバイザーは候補となる買い手企業をリストアップし、比較的条件が合いやすい会社を紹介してくれます。
個人的に打診することも可能ですが、アドバイザーを通して買い手企業を選定した方が手間もかからずに済むでしょう。
打診する際にはあらかじめノンネームシートを作成しておき、秘密保持契約を締結させてから話し合いを進めていきます。
秘密保持契約が締結したら、双方のトップ同士で面談を行います。
自社が相手の会社を見極めることも重要ですが、こちらも見極めの対象となっていることは忘れないようにしてください。
分からないことがあれば、トップ面談できちんと尋ねておき不明点をなくしておきましょう。
その後、買い手企業から意向表明書が提出されます。
意向表明書には買い手企業の考えから譲渡金額、譲渡後の運営に関する事項など、様々な内容が記載されています。
意向表明書はあくまでも法的拘束力を持っているわけではありませんが、意向表明書の内容を踏まえた上で最終的な契約が締結されることがほとんどなので、しっかり意向表明書の内容と併せて正式に契約を結ぶか検討しましょう。
交渉手続きが進み、双方で同意すれば基本合意契約の締結となります。
基本合意書には事業譲渡における条件や今後予定されるデューデリジェンス、独占交渉権に関する事項などが明記されています。
基本合意書の内容も会社法で定義されていないため、案件によって内容が異なります。
記載内容をよく確認した上で、締結させましょう。
買い手企業がデューデリジェンスを実施し、社内の状態を調査します。
調査結果を基に、再度事業譲渡価額の算定を見直したり、どのようなリスクがあるかを検討したりしながら、事業譲渡契約書に必要事項を盛り込んでいきます。
ここで売り手企業が注意すべき点は特にないものの、調査時に必要な資料は不足のないように提出しましょう。
デューデリジェンス後も特に問題がなければ事業譲渡契約を締結させます。
事業譲渡を締結させたら、臨時報告書の提出(有価証券報告書の提出義務がある企業の場合のみ)や公正取引委員会への届け出(国内売上高合計額200億円以上の場合)が必要です。
また、事業譲渡の旨や株主総会の開催を株主へ通知、公告しましょう。
株主総会では、事業譲渡に関して株主から承認を得なくてはなりません。
株主は議決権の過半数以上が出席しており、なおかつ2/3以上の賛成があれば事業譲渡の承認となります。
略式事業譲渡・簡易事業譲渡は実施する必要もありません。
事業譲渡を行う際に、名義変更や許認可変更の手続きを行わなくてはなりません。
手続きが済んでいないと、譲渡後にも事業がスタートできなくなってしまうため、必要な手続きはすべて完了させておきましょう。
特に許認可手続きは業種によって取得条件があったり、時間がかかったりする場合があるので、早めに申請手続きを進めてください。
決済日には買い手側から売り手側へ譲渡代金が支払われます。
決済が行われるまでに、売り手側は事業の引き継ぎを完了させておきましょう。
事業譲渡は一事業が持つ資産や取引先、従業員、契約などを買い手企業へ譲渡する方法を指します。
同じM&Aスキームの1つでもある株式譲渡とは異なり、買い手側は負債を引き継ぐ必要がなく、簿外債務のリスクも回避できます。
売り手側も法人格を残しながら不採算事業を切り離せるので、主力事業もしくは新事業に注力したい場合におすすめです。
ただし、事業譲渡は負債の引き継ぎがない分、契約切り替えによって売上減少が生じたり、従業員が退職したりするリスクもあります。
このようなリスクを回避するためにも、事前の準備が重要となってきます。
専門家であるアドバイザーと相談しつつ、リスクを最低限に抑えた事業譲渡ができるようにしましょう。
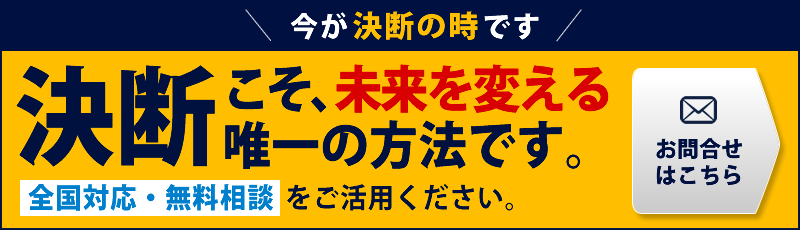
ご相談は無料です。お気軽にお声かけください。
Copyright© 2021 MAIN.co.ltd. All Rights Reserved.